2025年5月から、東京都のすべての都立学校で「生成AI」を使った学びがスタートしました。対象はなんと児童・生徒約14万人!今や仕事だけでなく、教育の現場にもAIが本格的に登場。未来の学びがどう変わっていくのか、ちょっと気になりますよね?

なお、この記事は東京都教育委員会のHPを参考にしています。


なぜ今、学校に生成AI?
最近、AIってよく聞くけど、「学校でも使えるの?」って思いますよね。
東京都では、子どもたちがこれからのAI時代を生きていくために、学校でもAIを使った学びを始めることにしたんです。
背景にあるのは「2050東京戦略」という未来に向けたプロジェクト。その中の「教育DX(デジタルトランスフォーメーション)」の一環として、生成AIを使って“考える力”や“創造する力”を育てようとしているんですね。
「都立AI」ってどんなサービス?
都立学校専用に用意されたのが「都立AI」というサービス。
これ、ただのAIじゃありません。教育向けにちゃんとカスタマイズされていて、
・安全面もバッチリ!
→ 入力内容はAIに学習されず、不適切なやりとりはブロック
・使いやすさも◎
→ 「こんな風に聞くといいよ」っていうテンプレートが最初から用意されています。
・授業でもすぐに活用可能
→ 探究学習や表現活動にぴったりな設計
・AIリテラシーの育成にも寄与
→ ハルシネーションやバイアスの可能性について、個人情報を入力しないということ、著作権に配慮すること 等
これなら、AIに不慣れな先生や生徒でも、すぐに使い始められそうですね!
安心して使えるための教材やガイドも!
「でも、AIってなんとなく不安…」そんな声もありますよね。



すべてポータルサイト「とうきょうの情報教育」で公開中なので、気になる方はのぞいてみてくださいね。
👉 情報教育ポータルはこちら
実際にやってみた!研究校のユニークな取り組み
試験導入された学校では、こんな面白い使い方がされていました!
-
ロボットのいいところ・悪いところをAIに聞いてみた!
→ いろんな視点を知って、ディスカッションが盛り上がる -
俳句やダジャレをAIと一緒に作ってみた!
→ AIが得意なこと・ちょっと苦手なことも発見 -
学校紹介動画のネタを考えてもらった!
→ 外部の人に伝わるように工夫しながら発信力アップ
これらのテーマは、東京都教育委員会が令和5年度に9校、令和6年度に20校指定した「生成AI研究校」での研究成果を踏まえ、全都立学校での生成AIを活用した学習を開始するにあたって示されたものです。
これなら授業ももっと面白くなりそうですよね!


これからの教育がどう変わるの?
生成AIの導入は、世界的にも教育現場に新たな風を吹き込んでいます。そして、教師の役割も「知識の提供者」から「学びの伴走者」へと進化しつつあるようです。
AIが情報の整理や提案を担うことで、先生はよりいっそう生徒一人ひとりの理解度や興味に合わせた指導が可能になるかもしれませんね!



🌍 世界のAI教育の取り組み
- アラブ首長国連邦(UAE):4歳からAI教育を導入し、年齢や学年に応じたカリキュラムで、AIの倫理的な使用やプロンプトの作成方法、AI生成コンテンツの評価方法などを教えています。
- シンガポール:「Smart Nation」戦略のもと、2030年までにAI教育の世界的リーダーを目指しています。特別支援が必要な子どもへの個別対応、AIによる自動採点、学習分析、個別フィードバックなどを導入。2026年までにすべての教師へのAI教育研修も予定されています。引用:The 74
- 韓国:AIを活用して生徒の学習傾向やレベルに合わせた課題を提供するシステムを導入。2025年3月からAIデジタル教科書を小3・4、中1、高1で導入。AIが学習進度や理解度に応じて教材を自動調整し、教師はファシリテーター役に。引用:The 74
- 中国(北京):小学校から高校まで、年間8時間以上のAI教育を義務化(2025年9月予定)。実践的なAIスキルの習得を重視しています。引用: Business Insider
- フィンランド:「Elements of AI」というオンラインコースを開発し、EU全体でAIリテラシーの向上を目指しています。
まとめ
東京都が始めた生成AIを活用した教育は、「これが未来の学びかもしれない」と感じさせる大きな一歩となりました。
専用AIサービス「都立AI」や、しっかりした教材・ガイドラインが整っているからこそ、安全かつ効果的に使えるのもポイントですね。
これからAIが当たり前になる時代、私たち大人も子どもたちと一緒にAIと学んでいきたいですね。




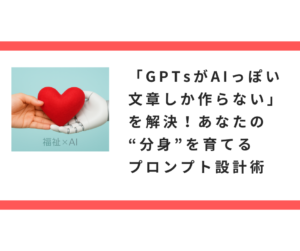

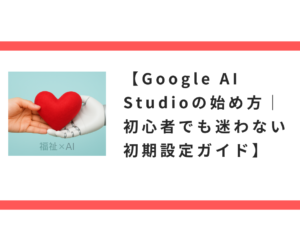
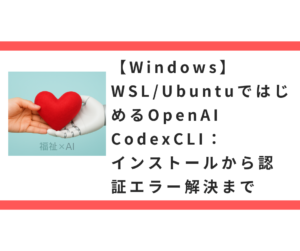
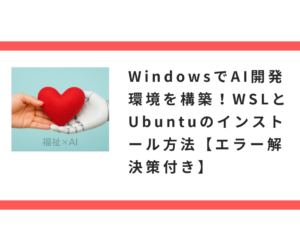
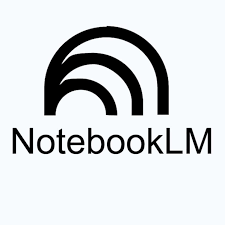


コメント